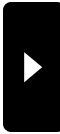2009年10月14日
六本木トライアングル
さて、今回の東京は結婚式とクラス会がメインだったんですが、
最近の帰省では、毎回なにかテーマを決めて気になるスポットをまわるようにしています。
前回はたしか鉄道と、なつかしい江戸情緒を感じる博物館や下町めぐり。
今回のテーマは、「スイーツ」と「蕎麦」と「アート」
(って、ふだんとあんまり変わってないがな^^;
ま、たまにはちょっとこじゃれたオシャレなスポットも行かないとねー
・・・なんせ、浦島太郎度はどんどん高くなってきてますもんねー(笑)
ということで、六本木の東京ミッドタウンへ。

この界隈には、国立新美術館、サントリー美術館、森美術館という
素晴らしいセレクションと入れものを誇る美術館が歩いていける距離にあり、
結ぶとちょうど三角形になることから、「六本木アートトライアングル」と呼ばれているんです♪
まずは「国立新美術館」へ。
でかいっ パッと見るとどこかのオフィスビルみたい・・・

でも変に凝った奇抜な造りではなく、展示室はまわりやすく見やすい。
そう、美術館の主役は建物ではなく作品!

「THE ハプスブルク」展は、
600年以上ヨーロッパに君臨した名門王家ハプスブルク家は、芸術をまもり愛したことで知られていますが、
その華麗な美術コレクションが宮廷肖像画とともに展示されています。
エル・グレコ、ベラスケス、ルーベンス、ブリューゲル、レンブラント、ラファエロ、ジョルジョーネ、デューラー・・・
美術の教科書に出てたっけなぁ~
象牙のような美しい肌、おだやかな表情の中で鋭く光るまなざし、聖書の一節を思わせる荘厳なシーン、光と影。。。
これぞヨーロッパの伝統的絵画!という雰囲気をひさしぶりに味わいました♪
「THE ハプスブルク」展
~12月14日(月)国立新美術館 (東京・六本木)
2010年1月6日(水)~3月14日(日)京都国立博物館 (京都・東山七条)
続いて、東京ミッドタウン内にある「サントリー美術館」で、
「美し(うるわし)の和紙~天平の昔から未来へ」展。

和紙をつかった古今の作品が展示されているんですが、これは予想以上に見応えがありました!
写真は、紅花やくちなしで和紙を染めた椿の造り花。
東大寺のお水取りで捧げられるものだそうです。
国宝や重要文化財の書間や写経、絵巻のほか、紙衣(かみこ)の着物(洗濯もできるそうで、びっくり!)や、蒔絵の文箱など芸術工芸品、紙すきの道具、襖や障子、提灯などの灯り、折り形(今の折紙)などもありました。
各地の和紙に触れられるコーナーも楽しい。
手触りがよくて目にやさしく、乾湿調節機能にすぐれそれでいて丈夫、というスグレモノ、
日本の暮らしには和紙が欠かせなかったんだなぁとあらためて感じます。
「美しの和紙~天平の昔から未来へ」展
~11月3日(火祝) サントリー美術館 (東京・六本木)
続いて、ちょっと歩いて六本木ヒルズの53Fにある「森美術館」で、
「アイ・ウェイウェイ展~何に因って?」展を。
北京五輪の鳥の巣スタジアムで一躍有名になった現代中国の代表的アーティストさんですが、
立体や写真、ビデオなど表現手法が多彩!
空間感覚を大切にする、という印象をもちました♪
「アイ・ウェイウェイ展~何に因って?」展
~11/8(日) 森美術館 (東京・六本木)
これら3つの美術館では、相互割引制度があり、もちろんこれを使いました^ ^
界隈には入場無料のフィルムセンターやギャラリーも多く、
さらには、東京都内66の美術館・博物館・動物園・水族園などの入場券や割引券がついた
おトクなチケットブック「東京・ミュージアムぐるっとパス2009」というものもあります。
東京メトロや都営地下鉄それぞれに乗り降り自由な1ディフリーきっぷもあるので、
うまく使って、アートなまち東京を楽しんでみるのもオススメ♪

さて、東京ミッドタウンを訪ねた目的がもう一つ、ここ、とてもエコなタウンでもあるんです。
敷地内に樹木を植えたり屋上緑化で緑を増やしてCO2を吸収させる、
ま、これは最近どこでもやっていますよね。
その他にも、雨水を緑の水やりに使ったり、雑排水を循環処理してトイレの洗浄水につかったり。
建物外壁のキラキラ光るルーバーは直射日光をさえぎるもので、
もちろん太陽光発電(ソーラー)や、水築熱システムなども。
そうそう、ゴミは16種類に分別!
うちのほうでも、「湖北ルール」でゴミ分別ではかなりの自負があるけど、
都会のど真ん中、しかもテナントの多いビルとしては、これかなり凄いことだと思いません?
もちろん今風にイメージをアップさせる「ウリ」として開発された側面もあるでしょうし、
本当に心底、環境のことを考えるのなら、
ビルをつくって人を集めたりなんてしないで、
「陽の明るいうちにみんな家へ帰って自炊しましょう」と呼びかけるほうが、
お金も環境への負荷も、かからないわけですけどね(笑)
それでも、こうやって都市が共生を考えてアピールしていくことは、決してムダではないと思いたい。
そういえば、まもなく「びわ湖環境ビジネスメッセ」のシーズン。
環境がビジネスとして成り立ってきた今、
今年はどんな未来へのビジョンを描いて見せてくれるのか、楽しみです♪
最近の帰省では、毎回なにかテーマを決めて気になるスポットをまわるようにしています。
前回はたしか鉄道と、なつかしい江戸情緒を感じる博物館や下町めぐり。
今回のテーマは、「スイーツ」と「蕎麦」と「アート」
(って、ふだんとあんまり変わってないがな^^;
ま、たまにはちょっとこじゃれたオシャレなスポットも行かないとねー
・・・なんせ、浦島太郎度はどんどん高くなってきてますもんねー(笑)
ということで、六本木の東京ミッドタウンへ。

この界隈には、国立新美術館、サントリー美術館、森美術館という
素晴らしいセレクションと入れものを誇る美術館が歩いていける距離にあり、
結ぶとちょうど三角形になることから、「六本木アートトライアングル」と呼ばれているんです♪
まずは「国立新美術館」へ。
でかいっ パッと見るとどこかのオフィスビルみたい・・・

でも変に凝った奇抜な造りではなく、展示室はまわりやすく見やすい。
そう、美術館の主役は建物ではなく作品!

「THE ハプスブルク」展は、
600年以上ヨーロッパに君臨した名門王家ハプスブルク家は、芸術をまもり愛したことで知られていますが、
その華麗な美術コレクションが宮廷肖像画とともに展示されています。
エル・グレコ、ベラスケス、ルーベンス、ブリューゲル、レンブラント、ラファエロ、ジョルジョーネ、デューラー・・・
美術の教科書に出てたっけなぁ~
象牙のような美しい肌、おだやかな表情の中で鋭く光るまなざし、聖書の一節を思わせる荘厳なシーン、光と影。。。
これぞヨーロッパの伝統的絵画!という雰囲気をひさしぶりに味わいました♪
「THE ハプスブルク」展
~12月14日(月)国立新美術館 (東京・六本木)
2010年1月6日(水)~3月14日(日)京都国立博物館 (京都・東山七条)
続いて、東京ミッドタウン内にある「サントリー美術館」で、
「美し(うるわし)の和紙~天平の昔から未来へ」展。

和紙をつかった古今の作品が展示されているんですが、これは予想以上に見応えがありました!
写真は、紅花やくちなしで和紙を染めた椿の造り花。
東大寺のお水取りで捧げられるものだそうです。
国宝や重要文化財の書間や写経、絵巻のほか、紙衣(かみこ)の着物(洗濯もできるそうで、びっくり!)や、蒔絵の文箱など芸術工芸品、紙すきの道具、襖や障子、提灯などの灯り、折り形(今の折紙)などもありました。
各地の和紙に触れられるコーナーも楽しい。
手触りがよくて目にやさしく、乾湿調節機能にすぐれそれでいて丈夫、というスグレモノ、
日本の暮らしには和紙が欠かせなかったんだなぁとあらためて感じます。
「美しの和紙~天平の昔から未来へ」展
~11月3日(火祝) サントリー美術館 (東京・六本木)
続いて、ちょっと歩いて六本木ヒルズの53Fにある「森美術館」で、
「アイ・ウェイウェイ展~何に因って?」展を。
北京五輪の鳥の巣スタジアムで一躍有名になった現代中国の代表的アーティストさんですが、
立体や写真、ビデオなど表現手法が多彩!
空間感覚を大切にする、という印象をもちました♪
「アイ・ウェイウェイ展~何に因って?」展
~11/8(日) 森美術館 (東京・六本木)
これら3つの美術館では、相互割引制度があり、もちろんこれを使いました^ ^
界隈には入場無料のフィルムセンターやギャラリーも多く、
さらには、東京都内66の美術館・博物館・動物園・水族園などの入場券や割引券がついた
おトクなチケットブック「東京・ミュージアムぐるっとパス2009」というものもあります。
東京メトロや都営地下鉄それぞれに乗り降り自由な1ディフリーきっぷもあるので、
うまく使って、アートなまち東京を楽しんでみるのもオススメ♪

さて、東京ミッドタウンを訪ねた目的がもう一つ、ここ、とてもエコなタウンでもあるんです。
敷地内に樹木を植えたり屋上緑化で緑を増やしてCO2を吸収させる、
ま、これは最近どこでもやっていますよね。
その他にも、雨水を緑の水やりに使ったり、雑排水を循環処理してトイレの洗浄水につかったり。
建物外壁のキラキラ光るルーバーは直射日光をさえぎるもので、
もちろん太陽光発電(ソーラー)や、水築熱システムなども。
そうそう、ゴミは16種類に分別!
うちのほうでも、「湖北ルール」でゴミ分別ではかなりの自負があるけど、
都会のど真ん中、しかもテナントの多いビルとしては、これかなり凄いことだと思いません?
もちろん今風にイメージをアップさせる「ウリ」として開発された側面もあるでしょうし、
本当に心底、環境のことを考えるのなら、
ビルをつくって人を集めたりなんてしないで、
「陽の明るいうちにみんな家へ帰って自炊しましょう」と呼びかけるほうが、
お金も環境への負荷も、かからないわけですけどね(笑)
それでも、こうやって都市が共生を考えてアピールしていくことは、決してムダではないと思いたい。
そういえば、まもなく「びわ湖環境ビジネスメッセ」のシーズン。
環境がビジネスとして成り立ってきた今、
今年はどんな未来へのビジョンを描いて見せてくれるのか、楽しみです♪
2008年08月19日
お江戸メトロさんぽ
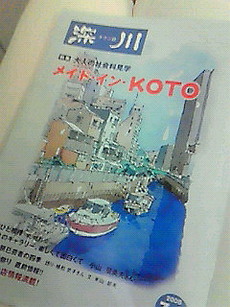



昨日はレトロな路線列車の旅でしたが、
せっかくなので帰る前に一応、東京でもっとも新しい路線と駅にも乗っておこう!
ということで、先日開通したばかりの副都心線に乗り、「新宿三丁目」駅で下車。
…というのはじつは偶然で、
うちの最寄り駅からこの副都心線へも直通があり、
今日いつものようにホームにかけあがり、来た電車に乗ったら間違えたのでした(^^ゞ
昨日の土合駅は、地下深く暗いモグラ駅で、歩いて階段を上がりましたが、
今日の新宿三丁目駅は、同じ地下でも、明るくてピカピカ光ってて、最新のエスカレーターとエレベーターで上へ。
新旧、違えば違うものですね〜
その後、東京メトロ半蔵門線に乗り「清澄白河」駅で下車。
ここは粋でいなせな下町、「深川っ子」のまち。
3年に1度の深川八幡祭りが終わったばかりで、ちょっと一息、といったところでしょうか^^
深川来訪の目的は2つ、
東京都現代美術館、そして深川めし♪
その向かう道すがら発見したのが、画像3枚目と4枚目。
22代目木村庄之助がいつ頃の人なのかわかりませんが、
そういえば、今度、米原にも大相撲が来るんだなあ♪
トンボは、道にはめ込まれた石畳の中の一枚。
他にも、ホタル、カタツムリ、クワガタ、などがいました。
こういう、一見気がつきにくい部分に、遊び心の感じられるまちって、好き♪
『タウン誌深川』によると、かき氷シロップの元祖や、ハンドクリームももの花を作っている会社なども近くにあるらしい。
古いものと新しいものとが溶け合ってるまち、という感じですね。
前回帰ったときの、谷中・根津・千駄木ツアーでも感じたことですが、
東京から、江戸や下町らしさの感じられるところが、どんどん無くなってきています。
バブルの頃の無茶苦茶な大変貌をくぐり抜けたまちも、今度のはそれとは明らかに異なる感じに変わってきている気がする。
たまに訪れる観光客の郷愁を満たすためのまちではなく、
そこに住む人が暮らしやすいまちへ。
よいことだと思う、それだけに、こまごまとしたいいモノをしっかり目に焼き付けておきたいし、
出来ることなんて無いんだけど、がんばってくださいねと応援したくなる、
おせっかいな私です。。(笑)
2007年10月17日
2007年10月16日
東京通信14〜これイイ感じ!編2
ちょっとイイ感じパート2は、乗り物まわり編♪
エコな暮らしが気になる昨今。
今回は意識して、移動は電車、地下鉄といった公共交通機関を利用したせいもあってか、
(てっちゃんだからでもあるけど(;^_^)
駅まわりが目につきました。
まずは、駅の献血ステーション。

いま何型の血が不足している、といった情報がわかりやすく公開され、
明るくて親しみやすい雰囲気が、いい感じ♪

駅の無線LANスポットはさらに拡大。

大阪、京都はだいぶ普及してきたけど、滋賀はまだまだ少ないもんね〜
人口がけた違いとはいえ、やはりうらやましい…(;^_^
草津にもできてる、クイック床屋さんが駅構内に。

10分で1000円、今の待ち時間がランプでわかるのがミソ?
電車の待ち時間にできる気軽さと安価のためか、
大繁盛。
宅配の本やCD受け取りサービスなんてのもあり、留守がちの人にはいいかも。
そういえば、これらの代金もだし、自販機、コンビニ、売店、その他かなりのモノやサービスが、
「スイカ」(ICOCAの関東版)で利用可能。
利用ポイントがたまればそれをチャージできるのは嬉しい。
一方バスはといえば、
ドア幅の広いノンステップ低床タイプがほとんどで、
車椅子やベビーカー、ご年配の方々も乗降しやすい配慮がされています。

信号待ちでのアイドリングストップ、これは見事なまでに徹底されていて、感心!
車椅子といえば、
電車に乗る際、ホームと電車の間に折り畳み式の板を渡して乗降されている光景を、
何度も見ました。
駅に備え付けのようで、
あれなら、サポートするのは誰でも一人で可能。
する側はもちろん、される側も負担にならなくて良いのではないかなぁと思います。
全体に、公共交通機関のエコ度や利用しやすさが
高まった印象。
古くて新しい乗り物、頑張ってるなぁ(*^_^*)
これって悪くないよね♪
エコな暮らしが気になる昨今。
今回は意識して、移動は電車、地下鉄といった公共交通機関を利用したせいもあってか、
(てっちゃんだからでもあるけど(;^_^)
駅まわりが目につきました。
まずは、駅の献血ステーション。

いま何型の血が不足している、といった情報がわかりやすく公開され、
明るくて親しみやすい雰囲気が、いい感じ♪

駅の無線LANスポットはさらに拡大。

大阪、京都はだいぶ普及してきたけど、滋賀はまだまだ少ないもんね〜
人口がけた違いとはいえ、やはりうらやましい…(;^_^
草津にもできてる、クイック床屋さんが駅構内に。

10分で1000円、今の待ち時間がランプでわかるのがミソ?
電車の待ち時間にできる気軽さと安価のためか、
大繁盛。
宅配の本やCD受け取りサービスなんてのもあり、留守がちの人にはいいかも。
そういえば、これらの代金もだし、自販機、コンビニ、売店、その他かなりのモノやサービスが、
「スイカ」(ICOCAの関東版)で利用可能。
利用ポイントがたまればそれをチャージできるのは嬉しい。
一方バスはといえば、
ドア幅の広いノンステップ低床タイプがほとんどで、
車椅子やベビーカー、ご年配の方々も乗降しやすい配慮がされています。

信号待ちでのアイドリングストップ、これは見事なまでに徹底されていて、感心!
車椅子といえば、
電車に乗る際、ホームと電車の間に折り畳み式の板を渡して乗降されている光景を、
何度も見ました。
駅に備え付けのようで、
あれなら、サポートするのは誰でも一人で可能。
する側はもちろん、される側も負担にならなくて良いのではないかなぁと思います。
全体に、公共交通機関のエコ度や利用しやすさが
高まった印象。
古くて新しい乗り物、頑張ってるなぁ(*^_^*)
これって悪くないよね♪
2007年10月16日
東京通信13〜これイイ感じ!編1
さてさて、今度はひさびさの東京で見つけた、
ケイミー的「これ、ちょっとイイ感じ!」編♪
まずは、まちなかで。
今回、特に目についたのは、スモーキングエリアです。

施設や店内だけでなく、まちなかでの分煙・禁煙は、かなり徹底されてきている感じですね。

これは、駅そばのスーパー駐輪場にある、荷物預りロッカー。

時間や大きさで金額が異なり、キーは無く携帯で開閉します。
エコ自動販売機もいくつか発見。
先日番組でも触れましたが、
自販機大国ニッポン、こういうのがどんどん出てきてほしいですね〜
もっとも、自販機に頼らないのがベターではあるのだけど(;^_^
次は、公共交通機関のイイ感じ編へ♪
ケイミー的「これ、ちょっとイイ感じ!」編♪
まずは、まちなかで。
今回、特に目についたのは、スモーキングエリアです。

施設や店内だけでなく、まちなかでの分煙・禁煙は、かなり徹底されてきている感じですね。

これは、駅そばのスーパー駐輪場にある、荷物預りロッカー。

時間や大きさで金額が異なり、キーは無く携帯で開閉します。
エコ自動販売機もいくつか発見。
先日番組でも触れましたが、
自販機大国ニッポン、こういうのがどんどん出てきてほしいですね〜
もっとも、自販機に頼らないのがベターではあるのだけど(;^_^
次は、公共交通機関のイイ感じ編へ♪
2007年10月16日
東京通信12〜華やかどころも
一応行ったので、アップしとこ(;^_^
学生時代、そしてオフィス時代に通ったところ。
渋谷駅まわりは相変わらず雑然としているけど、
青山通りに出ると、キャンパスの緑の森が目に入ります。

向かいには、国連大学本部と並んで、子どもの城、青山劇場。

交差点を麻布方面へとまわると、雰囲気も変わっていきます。

ギャラリー、骨董店、高級ブティックが多く、
もちろん学生の分際では眺めるだけでしたが、
いい目の肥やしになりました。
裏へ入ると静かな散歩道だったり、こじんまりしたカフェもあり、
今でも好きな界隈です♪
そのまま進んで、麻布から首都高下をまっすぐ行くと…
眠らない街、六本木!

このあたりはオフィス時代によく来ました。
昔からファッショナブルで国際色豊かな街だけど、
最近、地に足の着いていないセレブ感が鼻につくような気がするのは、
私だけかなぁ。。
アマンドと俳優座が健在だったので、ちょっとホッ♪

学生時代、そしてオフィス時代に通ったところ。
渋谷駅まわりは相変わらず雑然としているけど、
青山通りに出ると、キャンパスの緑の森が目に入ります。

向かいには、国連大学本部と並んで、子どもの城、青山劇場。

交差点を麻布方面へとまわると、雰囲気も変わっていきます。

ギャラリー、骨董店、高級ブティックが多く、
もちろん学生の分際では眺めるだけでしたが、
いい目の肥やしになりました。
裏へ入ると静かな散歩道だったり、こじんまりしたカフェもあり、
今でも好きな界隈です♪
そのまま進んで、麻布から首都高下をまっすぐ行くと…
眠らない街、六本木!

このあたりはオフィス時代によく来ました。
昔からファッショナブルで国際色豊かな街だけど、
最近、地に足の着いていないセレブ感が鼻につくような気がするのは、
私だけかなぁ。。
アマンドと俳優座が健在だったので、ちょっとホッ♪

タグ :東京
2007年10月16日
東京通信11〜純大江戸たぬきそば
かどうかは定かではありませんが(笑)
これは典型的な関東型たぬきそばです。

あげかすには、かき揚げの名残りらしき桜海老もたまに混じっており、
なんだかとても得した気分♪
濃い醤油色が、これが良いのよね(*^_^*)
高校生の頃よく利用した駅そばのお店で、300円なり。
…ふと気がついた。
ふつう、女子高生が好んで立ち寄り、食べるものじゃなかったかも。
これは典型的な関東型たぬきそばです。

あげかすには、かき揚げの名残りらしき桜海老もたまに混じっており、
なんだかとても得した気分♪
濃い醤油色が、これが良いのよね(*^_^*)
高校生の頃よく利用した駅そばのお店で、300円なり。
…ふと気がついた。
ふつう、女子高生が好んで立ち寄り、食べるものじゃなかったかも。
2007年10月16日
東京通信10〜タイムスリップ
あった!

同窓会でまちの話になり、小中高と住んでいた辺りへぶらり。
駅はすっかり姿を変えていましたが、
歩いていくうちに、なつかしい地名、そして見覚えのある店もチラホラ。
記憶がだんだんよみがえり、
ここへ来て完全にデジャブー!
昼下がりのタコ公園、
ポコペンで友達と遊ぶおかっぱの私が、そこにいました♪


同窓会でまちの話になり、小中高と住んでいた辺りへぶらり。
駅はすっかり姿を変えていましたが、
歩いていくうちに、なつかしい地名、そして見覚えのある店もチラホラ。
記憶がだんだんよみがえり、
ここへ来て完全にデジャブー!
昼下がりのタコ公園、
ポコペンで友達と遊ぶおかっぱの私が、そこにいました♪

タグ :タコ公園
2007年10月15日
時代♪
鉄道博物館その4は、おもしろ紙モノ編。
ビジネス特急の愛称募集。ひかり、こだまの誕生につながったんですね!

大正時代の貨物運賃ポスター。
絹織物、板、石炭など、当時の産物がわかります。

食堂車のご案内。
旅の気分を高めてくれますね♪

注意書き。
瓶、土瓶、丼を投げるな、と書かれています。

ポスターは時代を反映していて、
ついつい読みふけっちゃいます♪
最後に。
休憩スペースは至るところにあり、キッズスペースもあるので、ご年配やお子さん連れでも大丈夫。
ただ、シュミレーションなど体験各種は人気で混雑するので、入場したらまず予約を。
レストランとミュージアムショップもめちゃ混みなので、
早めに行くとか、食事は時間をずらしたり、
お土産は最初に選ぶのもオススメ!
3階展望デッキからは、
ミニ列車の走りや、横を通る本物の新幹線も見られて、
気持ちよいスポットになっていました。
てっちゃんだけでなく誰でも楽しめて、
入場料金(大人1000円、小中高生500円)のもとは十分取れると思います(笑)
滋賀からは遠いけど、関東に遊びに行く機会があれば、大宮は近いので、
ぜひお出かけしてみてくださいね♪
ビジネス特急の愛称募集。ひかり、こだまの誕生につながったんですね!

大正時代の貨物運賃ポスター。
絹織物、板、石炭など、当時の産物がわかります。

食堂車のご案内。
旅の気分を高めてくれますね♪

注意書き。
瓶、土瓶、丼を投げるな、と書かれています。

ポスターは時代を反映していて、
ついつい読みふけっちゃいます♪
最後に。
休憩スペースは至るところにあり、キッズスペースもあるので、ご年配やお子さん連れでも大丈夫。
ただ、シュミレーションなど体験各種は人気で混雑するので、入場したらまず予約を。
レストランとミュージアムショップもめちゃ混みなので、
早めに行くとか、食事は時間をずらしたり、
お土産は最初に選ぶのもオススメ!
3階展望デッキからは、
ミニ列車の走りや、横を通る本物の新幹線も見られて、
気持ちよいスポットになっていました。
てっちゃんだけでなく誰でも楽しめて、
入場料金(大人1000円、小中高生500円)のもとは十分取れると思います(笑)
滋賀からは遠いけど、関東に遊びに行く機会があれば、大宮は近いので、
ぜひお出かけしてみてくださいね♪
タグ :鉄道博物館
2007年10月15日
こんなんもあったねー
鉄道博物館その3は、グッズ編。
ヘッドマーク〜

乗車券箱。京福電気鉄道で使われていたものだそうです。

大正4年、京阪電気鉄道が日本で初めて導入した、色灯式信号機。現在でも一番多く使われているとな。

京都〜大津間開業の頃使われていた線路。
枕木は木ではなく、鉄製の変わった形。

信楽焼のお茶の土瓶。

この2階には、実際の部品を使って鉄道のシステムを楽しく学ぶ体験コーナーもあり、子どもだけでなく、大人もハマッてしまいます♪
お次は、おもしろ紙モノ編♪
ヘッドマーク〜

乗車券箱。京福電気鉄道で使われていたものだそうです。

大正4年、京阪電気鉄道が日本で初めて導入した、色灯式信号機。現在でも一番多く使われているとな。

京都〜大津間開業の頃使われていた線路。
枕木は木ではなく、鉄製の変わった形。

信楽焼のお茶の土瓶。

この2階には、実際の部品を使って鉄道のシステムを楽しく学ぶ体験コーナーもあり、子どもだけでなく、大人もハマッてしまいます♪
お次は、おもしろ紙モノ編♪
タグ :鉄道博物館